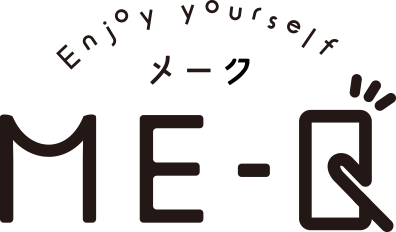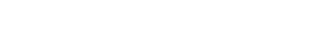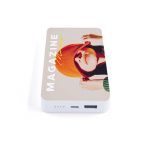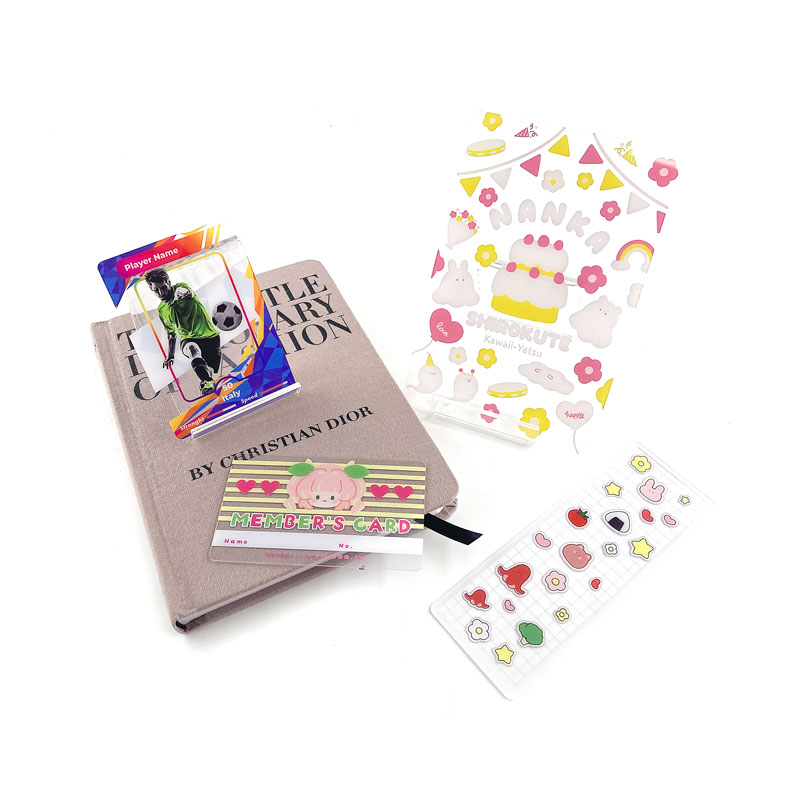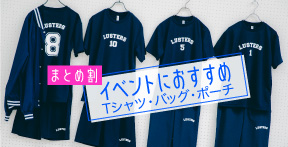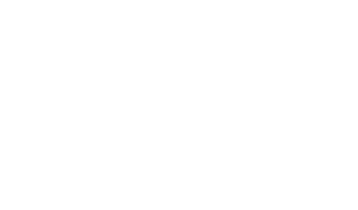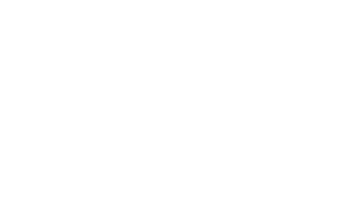モバイルバッテリーの容量によって使える時間は変わるの?その計算方法を解説します

スマートフォンを充電するのに必要なモバイルバッテリーですが、容量を確認して購入する必要があります。
この記事では、モバイルバッテリーの容量について解説するので、参考にしてみてください。
モバイルバッテリーの容量とは
基本的には自宅では、スマートフォンを充電できますが、外出先でバッテリーが切れると使えなくなってしまいます。
外出先でバッテリーが切れると、携帯電話やメールが使えなくなるだけではありません。
財布代わりに使用されているPayPayや切符代わりに使用されているモバイルSuica、他にもカメラや地図など基本的な機能が使用できなくなります。
モバイルバッテリーがあれば外出先でもスマホを充電できるので、日常的にスマートフォンを使う方からの需要は高くなっています。
外出先でバッテリーが切れるまで使用していなくても、使用するアプリや設定によってスマートフォンの消費電力は大きく異なり、予期せぬ電池の消耗を招く可能性があります。
スマートフォンの実用化が進む今、モバイルバッテリーは1つでも携帯しておくことをおすすめします。
ここでは、モバイルバッテリーを選ぶ上で重要なモバイルバッテリーの容量についてご紹介します。
モバイルバッテリーやスマートフォンのパッケージには、バッテリー容量の目安としてmAh(ミリアンペアアワー)と書かれています。
最近では、10,000mAhの大容量のモバイルバッテリーを見かけることも多いのではないでしょうか。
スマートフォンのバッテリー容量としては、iPhone8であれば2000mAh、やや大画面のものであれば3000mAh前後です。
自分が持っているスマートフォンのバッテリー容量とモバイルバッテリーの容量を照らし合わせて選ぶと良いでしょう。
mAhからWhへの変換方法とは
モバイルバッテリーやスマートフォンのバッテリー容量はmAhで表されますが、家庭用蓄電池や車のバッテリーであればWh(ワットアンペアー)と単位が異なります。
mAhとは、蓄えたエネルギーを1時間で放出した場合、どれだけの電流が流れるかを表しています。
Whとは、バッテリーに蓄えられる電力容量のことです。
Whが大きいバッテリーは、蓄えたエネルギーを1時間で放電しようとすると多くの電流を流せるため、mAh値も大きくなります。
つまり、mAhの数値が大きくなると、Whも大きくなるということです。
電力容量の変換式は、電圧にmAhをかけたものを1000で割ったものです。
mAhからWhへの変換方法は、モバイルバッテリーの電圧をmAhにかけると変換可能です。
現在、モバイルバッテリーやカメラのバックアップ用バッテリーに使われているほとんどがリチウムイオン電池です。
リチウムイオン電池の電圧は3.7Vなので、3.7VにAhをかけて、1000で割ると変換可能です。
モバイルバッテリーがリチウムイオン電池かどうかは、バッテリーの識別マークで確認してください。
お使いのモバイルバッテリーにLi-Ionと書かれたマークがあればリチウムイオン電池になります。
mAhからWhへ変換の計算をする際には、単位に注意してください。
mAh の場合は、流れる電流がA なのかmAなのかを明確にし、正しい単位を使用して計算する必要があります。
同様にWhも消費電力がWなのかkWなのか、時間の単位がh(時間)ではなくm(分)なのかs(秒)なのか注意が必要です。
単位を混ぜて計算しないように注意しましょう。
mAhとは
mAhはミリアンペアアワーと呼ばれる単位で、先程もご紹介した通りバッテリーの容量のことです。
自分の携帯のバッテリー容量が分かれば、何回充電できるかを計算できるため、全く知らなかった方はこの記事を読んで知識を身に付けておくことで、今後、役に立つでしょう。
もう少し詳しくmAhのご説明をします。
電流の単位であるAをご存知でしょうか。
mAはAの1000分の1の単位ですので、それにh(時間)をかけたものがmAhで、電気量を表します。
例えば、12,000mAhのモバイルバッテリーは、フル充電にした状態から充電がなくなるまで、12,000mAh分の電気量を携帯に送れます。
実際に充電できる容量とは
モバイルバッテリーのパッケージに売り文句として、容量と充電可能回数が記載されていることが多いです。
しかし、その充電可能回数を鵜呑みにしてはいけません。
実は、落とし穴が隠されています。
使用できる電力
モバイルバッテリーの容量と自分の携帯のバッテリー容量が分かれば、割り算して、何回充電できるか簡単に計算できます。
モバイルバッテリーの容量を選ぶ際には、5000mAhよりも10,000mAhを、10,000mAhよりも20,000mAhと値が大きい方がスマートフォンを多く充電できるため便利です。
自分のスマートフォンのバッテリー容量が3000mAhなのに対し、18,000mAhのモバイルバッテリーなので6回充電できるという計算は誤りです。
実際はモバイルバッテリーに記載されている容量の60パーセントから65パーセント程しか充電に利用できません。
商品や使用時間によって異なりますが、18,000mAhのモバイルバッテリーで3000mAhのスマホを充電できる回数は、18,000mAhを3000mAhで割って出た6回ではなく、多くても4回です。
なぜ、記載の容量の6割程度しか使用できないのかというと、昇圧に原因があるからです。
ほとんどのモバイルバッテリーは、リチウムイオン電池パックを1個から2個内蔵しています。
その電池パックの電力は約3.7Vの電圧で電力を送ることを想定したmAhになります。
iPhoneを充電する際のUSBの出力電圧は、5V必要なので、送れる電力は記載よりも減ってしまいます。
電池パックが1個の場合は内蔵の変換器により3.7Vから5Vまで昇圧しなければなりません。
また、電圧変換ロスといって、一旦5Vに電圧を変換してから送るため、変換するための電力もかかってしまいます。
セル容量18,000mAhのモバイルバッテリーで3.7Vに18,000mAhをかけて、約66.61Whの出力です。
これを5Vへと昇圧し、3.7Vの出力と比べると66.6Whを5Vで割った13,320mAhになり、容量が約74パーセントまで減少してしまいます。
また、3.7Vから5Vへの昇圧にはICの消費電力が伴います。
スマートフォンのICとは、集積回路のことです。
ICの消費電力による損失を10パーセントとして計算すると、実際の出力容量は約12,000mAhで、バッテリー容量3000mAhのスマートフォンであれば4回フル充電できるといえるでしょう。
損失は搭載するスマートフォンの IC によって若干異なり、5V での出力電力は表示値の 60パーセントから 70パーセント程です。
充電できる回数
充電に利用できる容量が分かれば、充電可能回数も分かります。
市販のモバイルバッテリーを使用して、スマートフォンを充電できる頻度を計算するには、表示された容量に 0.6 または 0.7 を掛けて計算してみましょう。
携帯の機種によってバッテリー容量は様々で、一度自分の使っている携帯の容量を確認する必要があるため注意しましょう。
また、充電してから時間が経過したり、使用回数が増えると、モバイルバッテリー自体の性能が低下する場合があります。
モバイルバッテリーの使用回数は、300回から500回程といわれています。
この回数は、モバイルバッテリーの種類や使い方によっても異なり、300回から500回使用したからといって、使用できないわけではありません。
本体の充電が完了するまでに時間がかかる、スイッチを押しても起動しにくい、バッテリーが膨らんでいる、バッテリーが熱くなりやすいなどの問題があれば買い替えましょう。
まとめ
今回はmAhやモバイルバッテリーの容量、充電できる回数について解説しました。
モバイルバッテリーの充電回数が計算できると、購入してからの混乱も少なくなるため参考にしてください。
モバイルバッテリーの容量に関して、お困りのことがあれば当社までご相談ください。
<h2 style="margin-top:100px;">こちらの関連商品をオリジナルで1個から作成頂けます。</h2> <div class="sim-block" data-sim-search="?keyword=&category=586"></div>